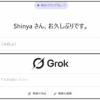2025年10月中旬のある日、24TB HDD(ハードディスク)を買った。
近年の自分のブログ記事は、比較的テーマがある記事を書くようにしていたが、所詮は個人ブログ、まあたまにはこんな日記みたいな雑文もいいだろう。
[推敲度 4/10]

【目次】
1■24TB HDDの価格下落
2■自作パソコンと近年(2010年以降)のHDD価格
3■そんなこんなで24TB HDD購入
4■大きさの表示と転送速度
5■終わりに
【本文】
1■24TB HDDの価格下落
これを読んでいる人なら当然知っているだろうが、昔は記憶装置と言えば専らHDD(ハードディスクドライブ)だった。しかし昨今はSSD(ソリッドステートドライブ)が置き換わり始めている。特にコンパクトさを要求されるノートパソコンではHDDである製品の方が少数派になっているかもしれない。
だが容量が大きいのはなんと言ってもHDDだ。たとえば2025年10月現在、2-3万円を払えばHDD(3.5インチ)なら10TB以上が余裕で買えるが、SSD(2.5インチ)ならばせいぜい4TBだ。剛毅に10万円以上払うつもりなら、HDDは30TBのものがあるが、SSDは8TBしかない。
そして最近、特に値段の下がりが著しいのが24TB HDDだ。
秋葉原のHDDの価格を長期的にウォッチしているサイトに「サハロフの秋葉原レポート」というところがあり、その中の「HDD 価格推移・容量別」を見るとHDD価格動向が一目で分かる。
これを見ると特に2025年の値段の落ち方の激しいのが24TB HDDなのは一目瞭然だ。
「サハロフの秋葉原レポート」の「HDD 価格推移・容量別」より転載。赤丸は高崎によるもの。
自分が買った24TBは45000円ということで
1845円/TB、1.85円/GB
となり、単価あたりの値段では一番安くなっている。
2■自作パソコンと近年(2010年以降)のHDD価格
自分は自作パソコン使用者だ。自作パソコン利用者、すなわち自作パソコンを作って使用する人を「ジサカー」というらしい。自分もジサカーの端くれだと思うし、その経歴25年ほどになるが、しかし熱心なジサカーとは言い難い。
たとえば自作パソコンでは「CPU+マザーボード+メモリ」の組み合わせの変更が、「パソコンの更新」「買い替え」というべきものだと思うが、自分はこの20年間、2006年、2014年、2024年とかの頻度でしかしていない。
そんな軟弱ジサカーの自分も、自作PC絡みでの、世界に誇れる(?)自慢がある。詳細な自作パソコンパーツ構成変遷を記録、公開していることだ。
これを見ると、メインパーツは長年更新していなくても、ハードディスクはちょろちょろと更新しているのが分かる。ハードディスクは何やかかやと容量が大きいのが欲しくなり、整理したくなるからだ。ハードディスクの空き容量が何やかやで減っていく、すなわちデータがすぐにいっぱいになる、というのは「冷蔵庫の法則」だと聞いていたが、これはもともと「パーキンソンの法則」というらしい。
自分の自作パソコン内も、6TBほどの比較的大きいパーティションが2つとも残り数百GBとなり、片方は赤いバーになってしまっていた。

他のドライブには空きが結構あるので、このハードディスク状況は逼迫しているという程の状況ではない。しかし昨年の秋にここ数年懸案だった「CPU+マザーボード+メモリ」の更新が終了、その後発生した不具合をこの前の夏に解決した、という「自作PC、整備している感」がHDDの更新を気持ち的に促した面があると思われる。
とはいえ、資金には限りがある。20年ほど前は自分はハードディスクにはせいぜい1~2万円しか出さなかったが、近年は3万円台までが自作パソコンのストレージに出せる金額としていた。最近のHDDとしては2023年10月に買った14TBが最大容量、歴代最大値段であった(36300円、単価2600円/TB)。この時は悩みに悩んだ決断で、というのも、2018年と2019年に8TB HDDを2万円弱(単価2350円/TBくらい)で買って以来、なかなかHDDの価格が下がらなかったからだ。
実際、上述したサハロフ氏のサイトのグラフ(HDD 1GB単価推移 / 対数表示)で見ると2020年あたりから単価あたりの価格が下がらなくなっており、しかも2023-2024年頃は上昇してしまっている。
「サハロフの秋葉原レポート」の「HDD 価格推移・容量別」より転載。赤丸は高崎によるもの。
調べるとSSDの需要の増加によりHDDの需要の減少による価格競争の減少、技術の停滞、そして円安の進行があったようだ。
記憶装置すなわちHDDやSSD、そしてメモリーカードなどは、時間が経てば安くなるのが当然、そういう時代を長く過ごしてきた身からすると価格が上昇するというのはびっくりである。
もっとも、上のグラフを見ると、そもそもそれ以前、2010年頃から、単価価格の下がり方はそれまでに比べるとなだらかになっている。2010年と言えば、自分は1TB製品のHDDを導入したころだが、昔はHDDは買う度ごとに値段は大して変わらずに倍々容量になっていたような気がするが、TBの製品時代になって随分鈍化した感じがある。
HDDの容量がどんどん大きく、安くなっていた頃は、HDDを買うなら前よりも大きいのを買おう!というポリシーで、仮に自作パソコン現行用で無くても、新しいものは大きいのを買って、前の容量が小さくなったのを別に転用、とう感じだった。ところが容量の大きい製品が十分値段が落ちなくなり、その結果8TBなどは半年おいて2台買い、2台目の方が価格が上がってしまったり、別目的での購入として、今までで買った容量よりも小さい製品を買う羽目になった。
3■そんなこんなで24TB HDD購入
ところが24TBが4万円台前半になったのだ!単価1800円/TB。
2014年に自分は6TBを23480円で買って以来、TBあたり2000円台が続き、しかもそれが上下していたのが、初の2000円を切る価格になったのだ!
実際には買う前にはこんな計算はしていない。だが、今までの感覚で24TBが4万円台前半は安い!とピピピと来たのである。
だが購入を躊躇わせる私的事情があった。昨年のマザーボード交換の最終仕上げと言うべき、システムドライブをSATA SSDからm.2 NVMe SSDに交換しようと、SSDを9月上旬に購入していたが、面倒でまだ取り付けておらず、積んだままにしていたのだ。自作PCパーツを買ったまま一ヶ月以上も取り付けず、また別なパーツ(24TB HDD)を買うなんて、、、という思いを抱いていた。
しかし、以下のようなことを考えるに至った。そもそも、昨今全盛になっているm.2パーツは自分は大嫌いだ。なんであんなに取り付けにくい機器、ホットスワップも出来ない機器が主流になってしまったのか。以下のブログ記事でも触れている。
「10年ぶりマザーボード交換~Core i第4世代からSocketAM5へ」(2024/11/25)
6.M.2接続が全盛?のようだが使いにくい。
それに対してSATAは大好きで、そもそも今の自作パソコンケースはSATA機器を取っ替え引っ替え出来る仕様にしてある。
上の記事「3.マザーボードへの拘り!一般にはSATAポートは減ってしまったが、最低6個は欲しい」
そんなわけで、m.2が購入後一ヶ月も放置なのは俺のせいじゃない、m.2の仕様か悪い。それに対してSATAである24TB HDDはすぐに活用できる自信がある。そんな言い訳を思いついて、24TB HDDを買うことにしたのだった。
4■大きさの表示と転送速度
最近のストレージは商品の記載容量とWindowsでの容量表示が結構違う。今回の24TBという商品もWindows上で見ると22TBほどしかない。
これは昔、
1KB=2の10乗=1024バイト
という表示で表す習慣と
1KB=1000バイト
という表示で表す習慣で分かれていたが、1998年に前者は
1KiB(キビバイト)=1024バイト
とされることが国際電気標準会議(IEC)というとこ決まった。ところがWindowsOSはキビバイトでの計算でありながらキロバイトの表記をしているとのこと。その結果
1TB=10の12乗
1TiB=2の40乗
となり、後者は前者より10%近く大きい。すなわち、Windowsは22TBと表示しているが、実際には22TiBであり、それは前者の24TBに合致するというわけだ。
この差はKB→MB→GB→TBと単位が上がるにつれて大きくなるので、昔に比べるとなんだか大きく感じるようになったわけだ。
ちなみにマイクロソフトとしては昔からの経緯や互換性の点から今更新しい単位を提唱されても安易に導入できるか、という感じのようだ。
購入後、データ移行を行ったのでその時の転送速度を参考までに示しておく。
パーティションワークス15:
5.3TB 6時間→245MB/s
4.4TB 8時間半→143MB/s
エクスプローラ:150MB/sなど
5■終わりに
以上のような経緯で24TBを購入、データ移行も概ね終えた。今まで
システムドライブSSD+14TB HDD+8TB HDD
という構成だったものが、最終的には
システムドライブSSD+14TB HDD+24TB HDD
となる予定だ。
新しいHDD1個(24TB)だけで、既存の2個のHDD合計(22TB)を上回る、こういうのは自分には今まであまり無かったようだ。
購入した値段(ほぼ45000円)としては3.5インチHDD歴代最高額となったが、単価は初めて2.0円/GB(2000円/TB)未満となった。これで不具合さえ出なければまあ満足な買い物だと思いたい。